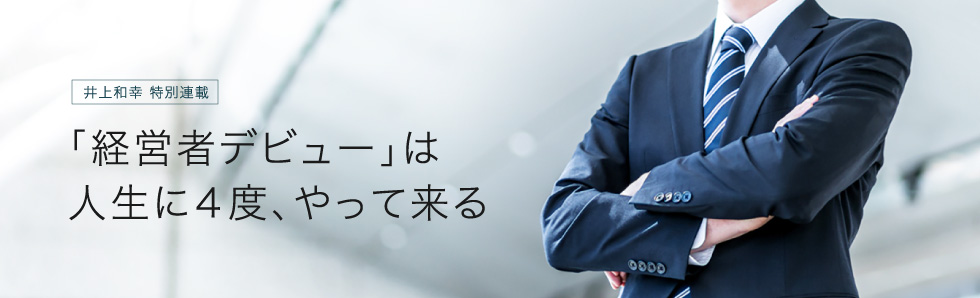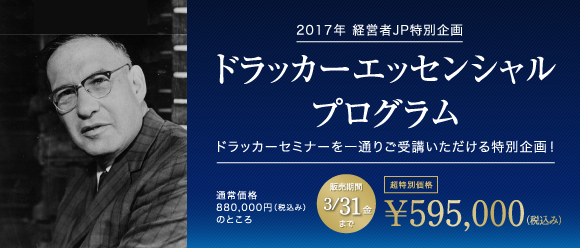VOL.3 世代ごとに学ぶべきことは異なる(座学編・前編)
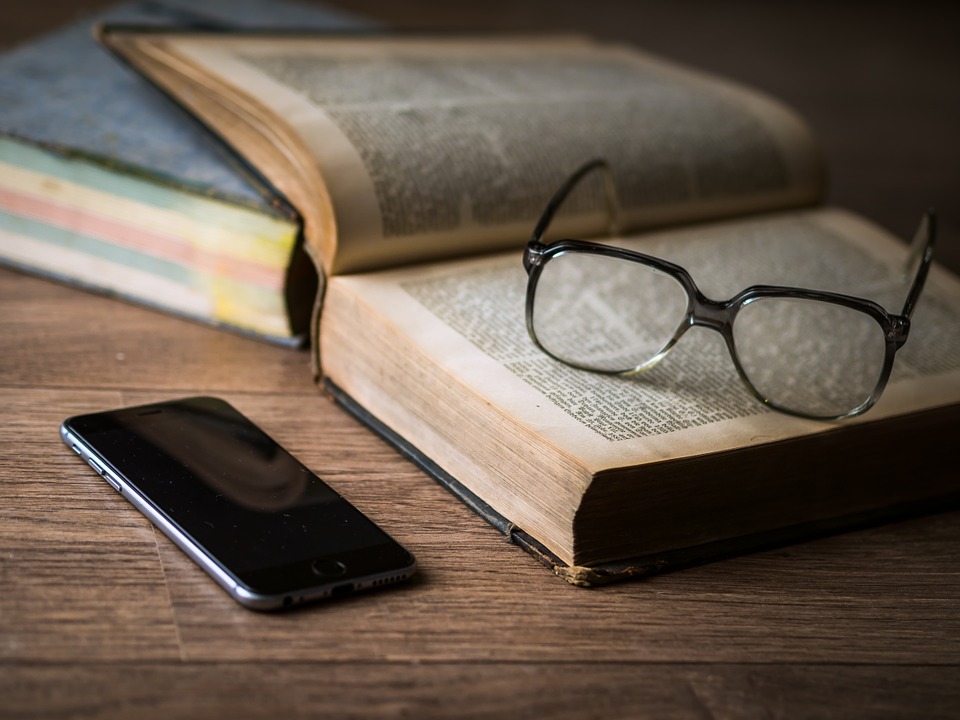 「社会人になってから一番役に立つ教科は何だろう?」
「社会人になってから一番役に立つ教科は何だろう?」先日、この連載の打ち合わせをした際に、こんな話題で盛り上がりました。スタッフの一人が、「最近、小学生の息子から質問をされ、それに答えることで勉強の大切さについてよく話し合うことができた」と言ったのがきっかけです。
私の考えを言えば、勉強はどの科目も大事ですが、ベースになるのは、やはり「国語」と「数学」になると思います。
「国語」については、表現力やコミュニケーション能力、情緒、感性といったものを身に付けるために必要ですし、一方、「数学(算数)」の基礎は、ロジカルシンキングや構造的理解をしていくうえで欠かせません。この両者の背後には、歴史や科学といった重要な知識があり、そうして身に付けた力や知識をベースにして、われわれビジネスパーソンは、経済や経営や組織などを学んでいきます。
特に経営者には、事象を構造的に捉える力や、自分なりのロジックで自分の考えを語り(書き)、人を動かしていく力が必要です。
それは他の職業、例えば、芸術家(アーチスト)などでも実は同じでしょう。この分野で大成功している人たちは、表現力や感性が突出しているだけではなく、自分の作品などについて非常に論理的に語れる人であることが多いのです。
例えば、映画監督の北野武さん(明治大学工学部を中退)は、その作品を数学的(因数分解的)な発想で編集している、と何かのインタビューで読みました。
だから、仕事をする上で、すべての力の大本となる「国語」と「数学(算数)」はしっかり勉強しておく(させる)べきだ、と私は思います。
もっとも、過ぎてしまった子供時代、学生時代の勉強について今さらあれこれ言っても仕方ありませんので、本連載では今回から数回にわたって、《リーダー・経営者をめざす社会人の方が勉強しておくべきこと》を年代別に考えていきましょう。
今回は、特に20代、30代の方が学んでおくべき知識(座学)に関して記します。
社会人の座学といえば、基本は読書です。私は、数多くの事業家や経営者の方にお会いしてきましたが、彼らは多忙な中でもたくさんの本を読んでいました。「読書家」とまでは言えなくても、本を読む習慣を持たずに大成功したビジネリーダーに、少なくとも私はこれまで会ったことがありません。
ビジネスパーソンとして成長したければ、年齢に関係なくさまざまな分野の本を読むべきですが、その中でも、20代では特に「志学」を、30代では「実学」を学ぶとよいでしょう。
「志学」というのは、自分の志を立てていくための読書です。例えば、古今東西の偉人や成功者の「伝記(評伝)」などがそうです。書籍に限らず、映画やドキュメンタリーも含めて、積極的に彼らの生き方や考え方に触れていくのです。
ただ、その一方で、目の前の仕事を成功させていくための「実用書」や「ノウハウ本」を読んでおくことも大事です。
そうした本を読むこと自体をバカにしたり、「どうせ役に立たない」と決め付ける人もいますが、先人や同業者の知恵がまとめられた本をバカにするのは間違いです。今まで役に立たなかったのは、自分の読み方が悪かったのかもしれないし、選ぶ本を間違っていたのかもしれないし、あるいは、読んでも行動していなかっただけかもしれません。
冒頭の話ではありませんが、振り返ってみれば、ノウハウ本を読まない人も、学生時代には、「これだけ覚えればOK!」とか「偏差値が20上がる〇〇の公式」みたいな参考書を買っていたはずです。それだけで合格することはありませんが、使い方次第ではとても効果があります。実用書やノウハウ本も同じです。
実際、私自身も、そうした本から得た知恵や知識にはずいぶん助けられてきました。本からも実務のノウハウを得たことで、仕事の成長スピードが速くなったと思いますし、そのときには使えなくても、後々、役に立つことがありました。
具体的な分野を挙げれば、すべてのビジネスの基本となる「セールス」と、消費者側の論理を理解できる「マーケティング」は、若いうちにぜひ学んでおくべきです。
次に、30代前半までの読書では、「経営書」や「ビジネス書」を徹底して読んでおきたいところです。この年代までに読書の習慣を定着させ、世の中のことを広く学び、実務力と人間力を高めていってほしいと思います。
具体的には、「管理会計」や「ロジカルシンキング」関連の本であり(これらは20代から読むべきですが)、その後に、「財務」や「経営戦略」へと展開していくとよいと思います。セールスやマーケティングでの学びを、事業レベルまで引き上げていくのです。
- 1
- 2