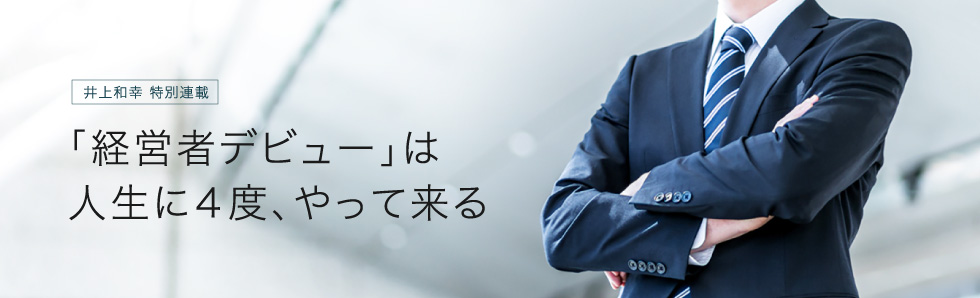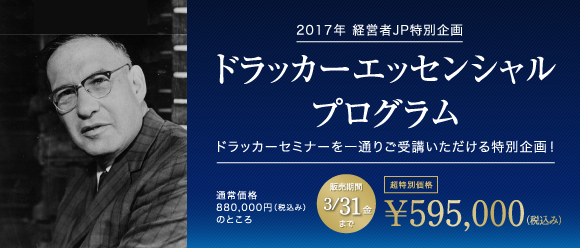VOL.4 30代以降に学んでおくべきこと(座学編・後編)
 先日、棋士の羽生善治さんが15年ぶりに「竜王」のタイトルを獲り、「永世七冠」の称号を得る偉業を成し遂げました。
先日、棋士の羽生善治さんが15年ぶりに「竜王」のタイトルを獲り、「永世七冠」の称号を得る偉業を成し遂げました。門外漢の私には、これがどれほど凄いことなのか本当の意味での実感までは持てないところもあるのですが、「永世七冠」というのは史上初の快挙にして、この先もあり得ないほどの偉業であるそうです。プロ野球で言えば、打率4割と三冠王を5回も6回も獲るような……、あるいは、オリンピック種目なら複数の金メダルを5大会も6大会も連続で獲るような話とも言えるのではないかと。とにかくすごいことです。
羽生さんはもう40代後半です。にもかかわらず、なぜ、そんなことが可能なのか? いくつかの記事で得た私の理解によると、羽生さんは、どんな大事な対局であっても、勝つ確率が高い、自分の得意な方法を選ぶのではなく、苦戦するのを承知で「相手の土俵(作戦)」に乗って戦うのだそうです。そうやって、学び、成長するチャンスを自ら創り出しているというのです。
これこそ、まさに前回までにお話しした、ビジネスパーソンが何歳になっても必要な「学び続ける力」だと思います。ビジネスの世界で言えば、これまでの経験で得た自分の得意技ばかりを使って楽をするのではなく、多少のリスクは負っても、常に新しい道を模索していくということでしょう。
この羽生さんの話は、私が過去にお会いしてきた経営者のお話や、渉猟してきた成功者の自伝・評伝の内容とも大いに重なります。つまり、成功者は「自分の中の基準」が高い。若いときから与えられた仕事を100%ではなく、150%、200%やろうとするところがあります。
私たち凡人から見ると、とてつもないと思えるような努力や偉業も、彼らにとっては「まだまだ不満」であったり、「単なる通過点」であったりします。こと学ぶ場面においても、「当たり前の基準」が他人と違うのです。
さて、そんな羽生さんをプロ中のプロの経営者と見立てて、今回は、前編に続いて「経営者をめざす人が30代以降に学んでおくべきこと(座学編)」の後編を記したいと思います。
経営者への道筋によっても異なりますが、一般的に30代以降のビジネスパーソンに求められるのは、「決める力(決断力)」、「まとめる力(リーダーシップ)」、そして、「描く力(構想力))です。
読書においては、年齢にかかわらず、どんな分野も本も幅広く読んでおくのが前提ですが、30代、40代は、前述の3つの力を身に付けることを意識して、個人レベルの学びから組織レベル、事業レベル、会社レベルの学びへとステップアップしていきましょう。
例えば、前編でも触れましたが、「セールス」と「マーケティング」の分野は、「(より実務的な)オペレーション」へ。同じく「管理会計」は、「財務」、「経営戦略」へと展開していきたいですね。
また、良きリーダーとなるためには、「マネジメント(人材管理)」、「心理学(社会学)」、「経営学」、「小説」などの分野を時間の許す限り読み、人間の原理原則について学んでおくことが大事です。
その一部を挙げれば、チャルディーニ、ドラッカー、コヴィー、カーネギーといった諸氏の著作のほか、孔子や孫子、ソクラテス、マキャベリ、アラン、日本人のものなら、鴨長明や吉田兼好などの「古典」とされているものがお勧めです。
さらに、注目したいのが、古今東西の「経営者の自伝(評伝)」です。これが大事なのは、学者やコンサルタントの書籍からは学べない、経営者やリーダーの「修羅場を潜り抜けた経験」や「経営・人間哲学」などを得ることができるからです。成功者たちが何を考え、何をめざし、何に失敗し、節目節目にどんな決断し、いかに飛躍して(あるいはピンチを切り抜けて)いったか――といったことを知り、それらに触れ続けることで、今後自分がなすべきことや、日々努力すべきことがわかるようになります。
具体的には、松下幸之助さんや稲盛和夫さん、柳井正さんをはじめとする名経営者たちの著作ですが、その他、地方の中小企業にも優秀な経営者はたくさんいらっしゃいますから、視野を広くして、機会あるごとに学ぶ姿勢が大事です。
- 1
- 2