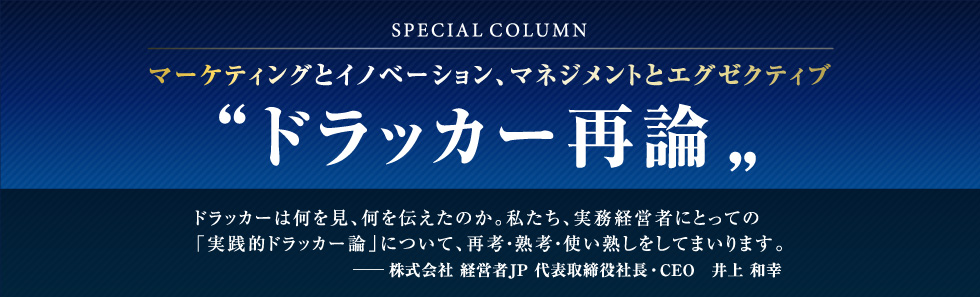事業の目的、ミッションを明らかにする上で、答えるべき最後の「
問い」は、「顧客にとっての価値は何か」
であるとドラッカーは言う。
「これが最も重要な問いである。しかし、
最も問うことの少ない問いである。
答えは明らかだと思い込んでいるからである」(『マネジメント–
-課題、責任、実践』、1973年)
現在開催中の経営講座「経営の父・ドラッカーに学ぶ、
経営者のためのトップマネジメント塾」(
https://www.keieisha.jp/seminar/170415/)でも前々回・前回とこれに取り組んだのだが、
参加経営者各位ともに1日の講座ワークが終わるところで、
まさに“ぐったり”(!)し尽くすくらい、
頭に汗をかく作業となる。
こればかりは、
実際に正面から取り組んだ方でしか味わえない感覚だろう。
多くの経営者が、「ドラッカー以前」には、「自社の商品・
サービスの品質こそが、顧客に提供されるべき価値である」
と答える。
それに対して、ドラッカーは、「
この答えはほとんど間違いである」と言い切る。
なぜだろう?
顧客は製品やサービスを買ってはいない。
自分の欲求の満足を買っているのだ。
レディスの服や靴があるとする。ティーンズにとっては、
それはファッションである。おしゃれが価値で、
価格や耐久性は二の次かもしれない。しかし、
主婦にとってのそれは耐久性、機能性や価格であることが多い。
ティーンズに価値があるものが、主婦には価値はさほどなくなる。
「顧客が買うものは価値である。これに対し、
メーカーが生産するものは価値ではない。
製品を生産し販売するにすぎない。したがって、
メーカーが価値と考えるものが、
顧客にとっては意味のない無駄であることが珍しくない」(『
マネジメント–-課題、責任、実践』)
別の例としてドラッカーは、
コピー機や自動車市場を取り上げている。
顧客にとっての価値は、
コピー機ではなくコピーすることそのものにある。
ゼロックスはこれを知り、コピー機ではなくコピー(複写)
に価格をつけることで成功した。
自動車市場は、
新車購入者にとっての自動車価格は新車の価格そのものだけでなく
中古車の下取り価格によっても購入意欲が左右される。
品質と単品の価格だけでなく、アフターサービスや、
取り扱う際の手間やその部分でのコストなども影響を及ぼす。
同じものが、一方は多少安いが取り付けの手間がかかり、
もう一方は多少高いものの取り付けがワンタッチで簡便であるとき
に、後者が圧倒的に売れるということはよくあることだ。
「顧客にとっての価値はあまりに多様であって、
顧客にしか答えられない。したがって、
答えを推察してはならない。直に聞かなければならない」(『
マネジメント–-課題、責任、実践』)
顧客にとっての価値から、
事業の目的とミッションが自動的に明らかになるわけではない。
しかし、事業を決めるものは世の中への貢献である。
貢献以外のものは成果ではない。
その成果に対して顧客が支払ってくれるものが事業収入である。
他のものはすべてコストにすぎない。
「外の世界、つまり市場から考えることが第一歩である。
すべてはその第一歩から始まる。そこから、
マネジメントが最初に行うべき最も基本的な意思決定の基盤をえる
ことができる」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)